
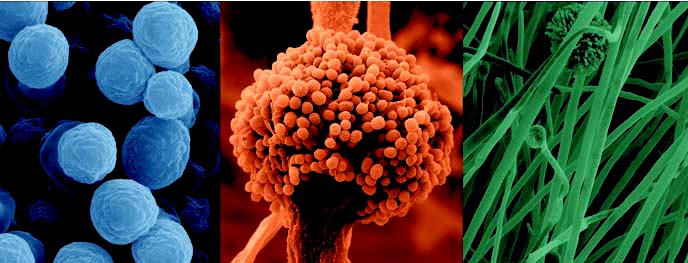
「塚越規弘先生のご逝去を悼む」
本研究会の第3代会長を務められ名誉会員でもあられた 塚越規弘先生が昨年の12月27日に84歳でご逝去されました。名誉会員であった飯村先生、別府先生に続いて、わが国の糸状菌の分子生物学研究の先端を開いていただいた一人でもある塚越先生までがお亡くなりになられたのはまことに残念でなりません。塚越先生は本研究会の第3代目の会長を平成20年(2008年)度から平成27年(2015年)度まで7年間務められ、その間に奨励賞および技術賞を設立されるとともに、平成26年には本研究会の25周年記念シンポジウムを企画され成功に導いてくださるなど、本研究会の発展に多大なる貢献をしていただきました。
塚越先生は1969年に東京大学大学院農学系研究科の博士課程を修了後、アメリカとスイスに8年間ほど留学されました。帰国後に出身の醗酵学研究室に研究生として一時在籍した時には私は修士課程の学生でしたので、先生とは研究室でご一緒したことになります。私は1978年に修士課程を修了して国税庁醸造試験所に入ったのですが、同じ年に塚越先生は名古屋大学農学部の鵜高重三先生の研究室の助教授として着任されました。先生は1988年には教授に昇進され、糸状菌、特にAspergillus nidulansと麴菌を対象にして、アミラーゼやセルラーゼ、キシラナーゼなどの有用酵素遺伝子の発現制御機構に関する研究を進められました。その研究業績により、1998年には日本農芸化学会賞を受賞されております。
塚越先生は教授に昇進されるにあたって糸状菌、特にコウジカビを対象とした研究を始めたいということで、私が開発していた麴菌の形質転換実験技術を学びに醸造試験所まで足を運ばれ自らその技術を習得して帰られました。その後、アミラーゼ遺伝子の発現制御機構解析では私と興味が重なることになったのですが、私が麴菌を対象にin vivo解析を、塚越先生はA. nidulansを対象にin vitro解析を行うというように住み分けしてもらい、お互いに情報交換しながら研究を進めることができました。そのおかげで私もそれなりの研究成果を挙げることができたことを思うと、塚越先生のお心遣いやご協力はとてもありがたく心から感謝申し上げたいと思っています。私が大学の研究室の後輩で短い期間ですが一緒に在籍していたことがあるのでしょうが、それ以外にも何かと相談に乗っていただいたこともありがたいことでした。
塚越先生は会長を退任されてから名誉会員に推戴されましたが、例会が東京で開催されていることや遠慮されたこともあるのか例会等に顔を出されることはあまりありませんでした。しかし、先生が設立した奨励賞や技術賞がしっかり引き継がれて糸状菌の遺伝子研究の発展に寄与していることは嬉しく思っていただいていたことと思います。そこで、そのような先生のお考えを大事にして、さらに若手研究者の奨励を図る目的で、今年度から若手研究者賞を設立することにいたしました。先生が設立した奨励賞や技術賞に加えて若手研究者賞の授与を通してこれからの研究会を発展させていくことも先生のご尽力に報いることになるものと思っています。
塚越先生のこれまでの研究会に対する多大なるご貢献にあらためて厚く感謝申し上げますとともに、心から哀悼の意を表します。本当にありがとうございました。
糸状菌遺伝子研究会 会長 五味勝也
Newsページに戻る
本研究会の第3代会長を務められ名誉会員でもあられた 塚越規弘先生が昨年の12月27日に84歳でご逝去されました。名誉会員であった飯村先生、別府先生に続いて、わが国の糸状菌の分子生物学研究の先端を開いていただいた一人でもある塚越先生までがお亡くなりになられたのはまことに残念でなりません。塚越先生は本研究会の第3代目の会長を平成20年(2008年)度から平成27年(2015年)度まで7年間務められ、その間に奨励賞および技術賞を設立されるとともに、平成26年には本研究会の25周年記念シンポジウムを企画され成功に導いてくださるなど、本研究会の発展に多大なる貢献をしていただきました。
塚越先生は1969年に東京大学大学院農学系研究科の博士課程を修了後、アメリカとスイスに8年間ほど留学されました。帰国後に出身の醗酵学研究室に研究生として一時在籍した時には私は修士課程の学生でしたので、先生とは研究室でご一緒したことになります。私は1978年に修士課程を修了して国税庁醸造試験所に入ったのですが、同じ年に塚越先生は名古屋大学農学部の鵜高重三先生の研究室の助教授として着任されました。先生は1988年には教授に昇進され、糸状菌、特にAspergillus nidulansと麴菌を対象にして、アミラーゼやセルラーゼ、キシラナーゼなどの有用酵素遺伝子の発現制御機構に関する研究を進められました。その研究業績により、1998年には日本農芸化学会賞を受賞されております。
塚越先生は教授に昇進されるにあたって糸状菌、特にコウジカビを対象とした研究を始めたいということで、私が開発していた麴菌の形質転換実験技術を学びに醸造試験所まで足を運ばれ自らその技術を習得して帰られました。その後、アミラーゼ遺伝子の発現制御機構解析では私と興味が重なることになったのですが、私が麴菌を対象にin vivo解析を、塚越先生はA. nidulansを対象にin vitro解析を行うというように住み分けしてもらい、お互いに情報交換しながら研究を進めることができました。そのおかげで私もそれなりの研究成果を挙げることができたことを思うと、塚越先生のお心遣いやご協力はとてもありがたく心から感謝申し上げたいと思っています。私が大学の研究室の後輩で短い期間ですが一緒に在籍していたことがあるのでしょうが、それ以外にも何かと相談に乗っていただいたこともありがたいことでした。
塚越先生は会長を退任されてから名誉会員に推戴されましたが、例会が東京で開催されていることや遠慮されたこともあるのか例会等に顔を出されることはあまりありませんでした。しかし、先生が設立した奨励賞や技術賞がしっかり引き継がれて糸状菌の遺伝子研究の発展に寄与していることは嬉しく思っていただいていたことと思います。そこで、そのような先生のお考えを大事にして、さらに若手研究者の奨励を図る目的で、今年度から若手研究者賞を設立することにいたしました。先生が設立した奨励賞や技術賞に加えて若手研究者賞の授与を通してこれからの研究会を発展させていくことも先生のご尽力に報いることになるものと思っています。
塚越先生のこれまでの研究会に対する多大なるご貢献にあらためて厚く感謝申し上げますとともに、心から哀悼の意を表します。本当にありがとうございました。
糸状菌遺伝子研究会 会長 五味勝也
Newsページに戻る